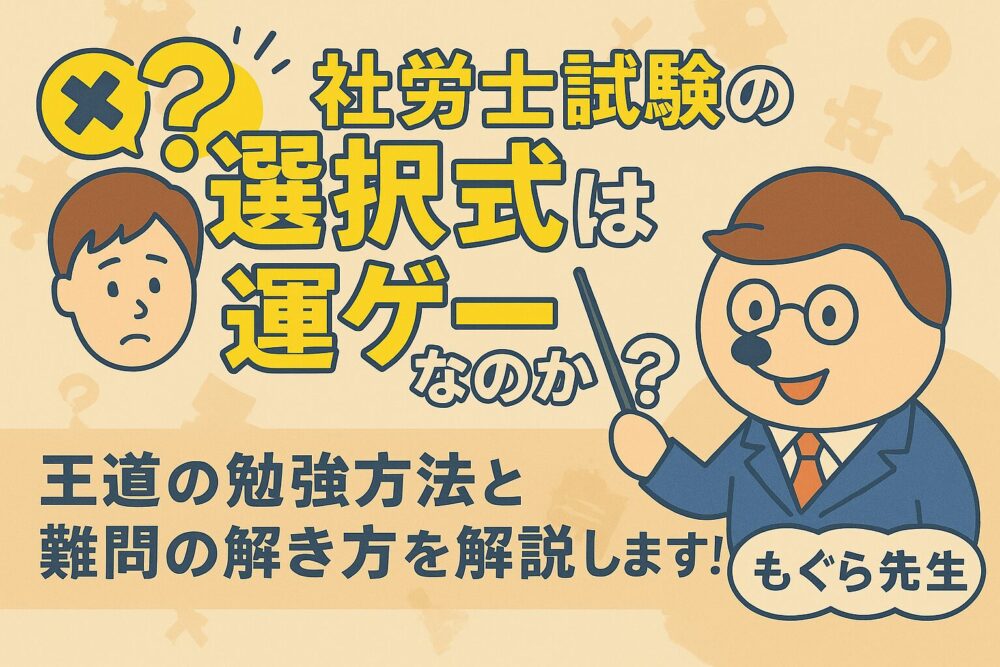こんにちは、社労士のタクヤです。

選択式の「あと1点」で落ちてしまった~
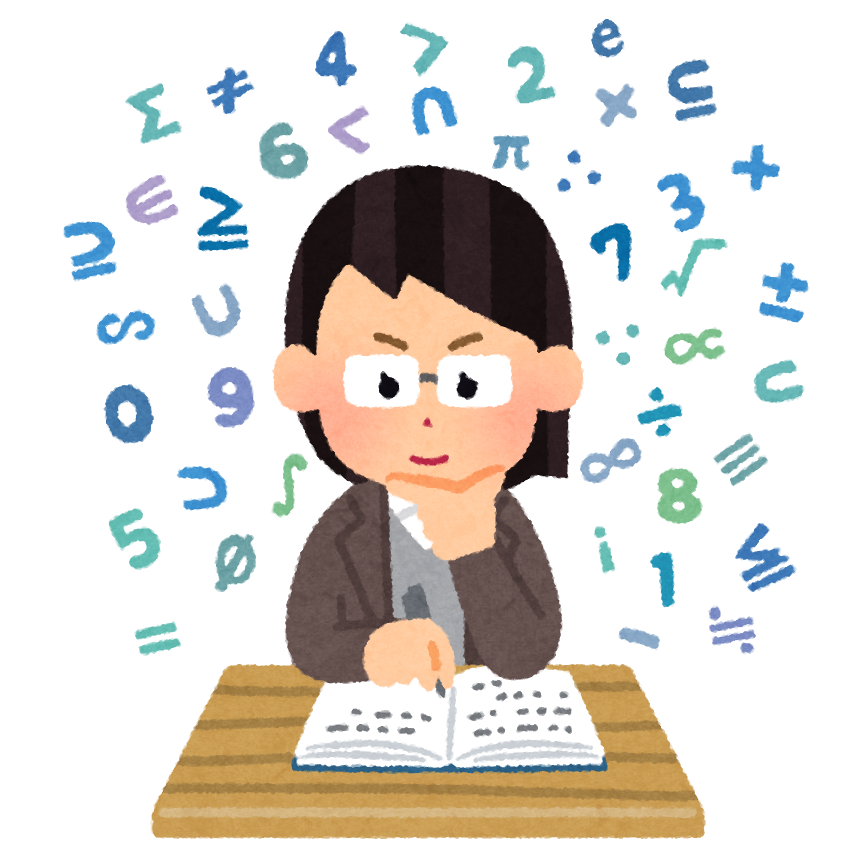
「知らない問題」は対策できないよ~
社労士試験の勉強をしている人なら、一度は聞いたことのあるでしょう。


それでもクリアするためにポイントは明確に存在する!
この記事でわかること
✅選択式の王道の対策と勉強方法
✅選択式の問題を解く最適な手順
筆者も実は救済で合格したのですが、
- 2年の受験勉強でバッチリ対策を行ったし、
- 5年間の受験講座の講師も経験してきました。

そんな筆者が合格に一歩近づく選択式対策を伝授していきますよ。
社労士試験の選択式が運ゲーだと言われる理由
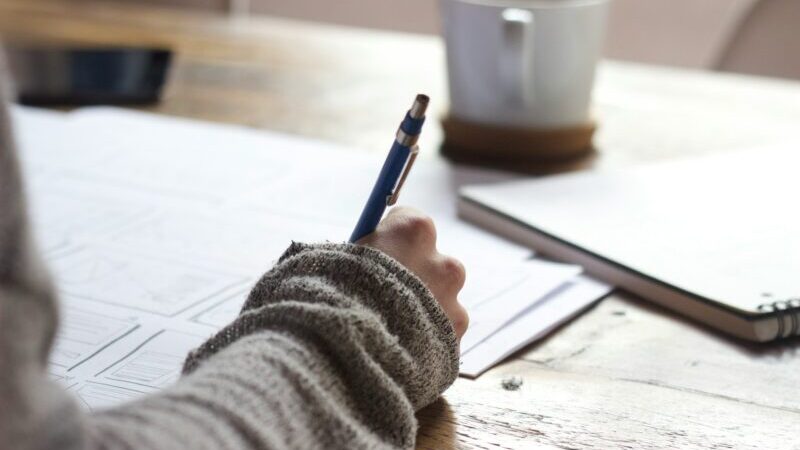
社労士の選択式試験は「運」の要素が大きいと言われます。

選択式の概要と合格基準点
選択式試験は8科目で、1科目につき5つの空欄があります。
| 科目の構成【( )内は点数配分】 |
| 労働基準法(3)・労働安全衛生法(2) |
| 労働者災害補償保険法(5) |
| 雇用保険法(5) |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識(5) |
| 健康保険法(5) |
| 国民年金法(5) |
| 厚生年金保険法(5) |
| 社会保険に関する一般常識(5) |
- 試験時間は80分なので1科目につき10分ですが、
- 簡単な問題は5分程度で解答できます。

だからこそ難問にはしっかり時間を使うのじゃ(^^)
合格基準は以下の2つを満たすことが条件になります。
- 総得点が一定以上であること
- 8問すべてが5点満点中3点以上であること
但し、年によっては合格基準点が引き下げられる「救済」が入ります。
ほぼ毎年救済が入っている
実は選択式試験では、救済が入っている年の方が多いです。
| 試験年度 | 救済の有無 | 選択式合格基準点(救済科目) |
| 2025年度 | あり | 22点(労災・労一・社一) |
| 2024年度 | あり | 25点(労一) |
| 2023年度 | 〈なし〉 | 26点 |
| 2022年度 | 〈なし〉 | 27点 |
| 2021年度 | あり | 24点(労一・国年) |
| 2020年度 | あり | 25点(労一・社一・健保) |
| 2019年度 | あり | 26点(社一) |
| 2018年度 | あり | 23点(社一・国年) |
| 2017年度 | あり | 24点(雇用・健保) |
| 2016年度 | あり | 23点(労一・健保) |

難問や奇問が必ず出題される
救済は入るのは、難問や奇問が出題されているからです。
難問や奇問の定義
✅各科目の理解しにくい論点の問題
✅ほとんどの受験生が初めて見る問題

そんな難問や奇問を解く上での前提が3つあるぞ(^^)
- 満点を取る必要はない
- 問題を解くテクニックが必要
- 最後まで絶対にあきらめてはいけない
選択式の難問・奇問が、社労士試験を合格する上で最も厄介になってきます。だからこそ、正しい対策と問題の解き方は理解しておきたいです。
社労士は運ゲー?選択式対策と勉強方法
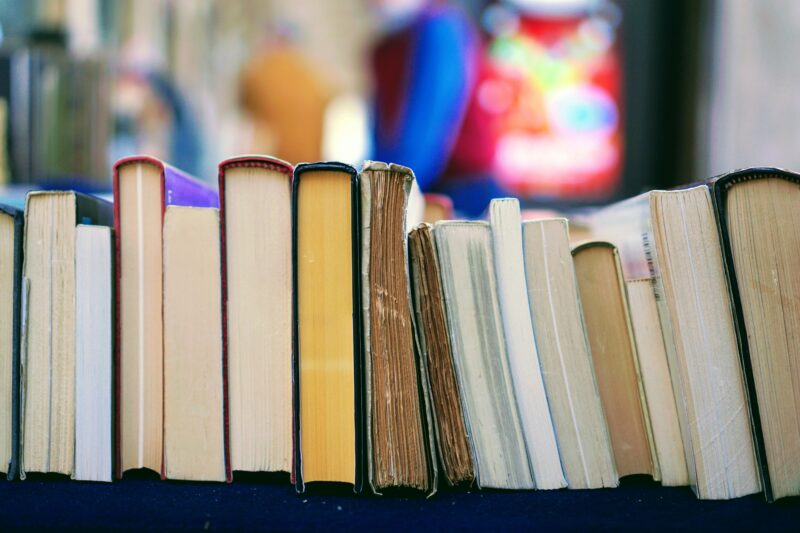
選択式の勉強方法に迷う人が多いですが、王道の勉強方法は存在します。

選択式対策をする上での前提
前提として、選択式には基本的な知識が必須です。
- 基本・基本の知識があってこそ、
- 具体的な対策の意味が出てきます。
「基本的知識」の定義
✅特別な対策なしでも難問や奇問以外は点数が取れる知識レベル
選択式で不合格になるパターンは2つあります。
- パターン1:複数の科目で3点(足切り点数)以下
- パターン2:1科目だけ3点(足切り点数)以下
断言しますが、パターン1の人は「基礎知識」の勉強が優先になるのが大前提です。

1年目は選択式ではなく、択一式で不合格点。翌年は選択式の対策に力を入れすぎて「択一式が不合格」という人もいます。まずは基礎知識が何より大切ですね。
択一式の過去問をしっかり解く
択一式の過去問を勉強することは、3つの理由で選択式にも大いに役立ちます。
- 選択式問題はほとんどは法律の条文から出題される
- 論点や内容を理解することに役立つ
- そのまま選択式で出題されるケースもある
択一式と選択式で出題形式は違っても、基本的な知識は同じです。
詳しい解き方は後で紹介しますが、
- 似ている選択肢から解答を選んだり、
- 前後の文脈から解答を導き出す。
最後はこんな解答テクニックも必ず必要になります。
選択式において、問題の論点を把握することは極めて重要です。なぜなら、論点を勘違いしていると解答も必然的に間違ってしまうからです。

テキストの赤字や太字を抑える
テキストの「赤字と太字」を意識して勉強することは対策として効果的です。
社労士の学習テキストは質が高いので、
- 重要なところ
- 暗記すべきところ
- 間違いやすいところ
などは目立つように記載されていますからね。

社労士の学習初期においては、
- テキストで科目の理解度を深めつつ
- 過去問で問題の論点を認識すること
を優先した勉強で問題ありません。
科目1周目は全体の理解を深めることを心がける。そしてGW辺りの時期からは、選択式対策も意識して「赤字と太字」を抑えていきましょう。
模試や予想問題を解く
選択式の対策において、模試や予想問題は大いに活用しましょう。
初めての問題を解くことで、
- 自分の客観的な実力を把握できる
- 問題の解き方のコツをマスターできる
- 本試験で同じ問題が出たら解答できる
など確実に実力をつけることができます。

解くだけではなく、振り返りも忘れずにな!
解き方のコツについては、後ほど詳しく解説しますので実践してみてくださいね。
選択式は難問・奇問が必ず出題されるので、基礎知識だけでは心配な要素がどうしても残ります。問題に慣れて実践の対策もしておきたいところです。

白書対策について
労一・社一で出題される白書は非常に厄介です。
- 範囲が膨大すぎる
- 難問、奇問が多い

厚生労働白書と労働経済白書を合わせると1,000ページ前後になりますが、それを全て熟読する必要はありません。
勉強方法として最低限すべきは2つです。
- テキストの赤字・太字を抑える
- 白書の概要・要約部分を把握する
白書対策については直前期に集中的に学習することをおすすめします。短期集中で大枠の傾向をインプットしましょう。
ちなみに白書対策は、可能なら予備校の直前講座を活用したいところです。
- 自己学習は極めて非効率
- でも全く対策しないのは不安
これらの問題はアガルート社労士アカデミーの直前講座で解決できます。

白書に力を入れ過ぎて、他の科目を落とすのは本末転倒じゃ!
社労士は運ゲー?選択式の問題を解き方

運ゲーだ!と思えるような難問・奇問でも解き方のコツは存在します。

まずはテーマと論点を理解する
選択式を解く時は、まず問題の内容を理解しましょう。
具体的には、
- 何のテーマについてなのか
- 何を論点としているのか
- 難易度はどれぐらいなのか
これらを問題を読んで認識します。
論点を理解した上で解くことで、焦らず落ち着くことができるんですね。
「木」を見て「森」を見ず。という“ことわざ”がありますが、これは選択式試験にも当てはまります。個別の選択肢だけに振り回されるのは危険です。
そして問題の全体像と論点を理解できたら、選択肢を見ずに解答を書いてみましょう。

選択肢を見ずに解答を書き出す
問題の内容を理解したら、選択肢を見る前に解答を書き出します。
この手順には理由があって、
- 書くことで解答を選びやすくなるし、
- より詳しく問題の論点が見えてきます。
選択肢に惑わされず、自分の知識を出すことで、混乱をなくすことができるんですね。

書き出すことで論点の整理になるんじゃ!
選択式の問題では、テーマや論点が複数存在するケースも少なくありません。書き出すことで、ケアレスミスをなくすことにも繋がります。

選択肢をグルーピングする
問題の全体像を理解したら、次は選択肢のグルーピングを行います。
選択式試験は、
- 1科目ごとに5つの空欄があり、
- 選択肢は20用語なので、
- 1つの問題に候補は4つ。
全てを20の選択肢で行うのではなく、4つを明確に絞る作業をグルーピングと言います。

この手法のメリットは3つで、とても効率的じゃ(^^)
- 頭を整理することができる
- じっくり丁寧に考えることができる
- ケアレスミスをなくすことができる
いかに焦ることなく、不必要な選択肢を排除して、丁寧に答えを導くことができるかが選択式問題を攻略する上では大切になってきます。

前後の言い回しから判断する
難問を解く時には、前後の文脈から解答を導き出すことが必須になります。
選択肢を当てはめてその前後を読むと、
- 重要なキーワードは何か
- 言い回しに違和感はないか
など問題の論点が見えてきます。
その中で、
- 文脈には合わない選択肢
- 似ているけど不適切な選択肢
このような「不正解の選択肢」も前後の文脈からわかってきます。
解答を4つの候補から選ぶ場合と2つの候補から選ぶ場合では正解率は大きく変わります。そのためにも、文脈から答え絞っていく必要がありますね。
基礎知識があるからこそ使える「前後の言い回しから判断する」という解き方です。

ダブルマークも最終手段
ダブルマークとは、同じ選択肢を2つの空欄に解答することです。
選択式試験では、合格基準点の「5点中3点」は必達です。
選択式試験
✅問題は5問:A・B・C・D・E
✅解答の選択肢:①~⑳
選択式試験は1科目につき5問を20の選択肢から解答しますよね。

そんな場面に遭遇することはあり得ます。

そんな時に3点を確実に取りにいくのがダブルマークじゃ!
- A・B・Cで2点は確実に取れている
- 「D④とE⑥」なのか「D⑥とE④」で迷う
こんな時の最終手段がダブルマークです。
組み合わせを外すと0点になってしまう。そこで、「D④:E④」のように同じ解答をします。これで確実に1点は得点できます。
全ての問題に活用できる訳ではないですが、一つのテクニックとして覚えておきましょう。

選択式対策に関するよくある質問3選

最後に「よくある質問」を筆者の講師経験を踏まえて3つに絞って解説していきます。
質問①ぶっちゃけ選択式試験は運ゲーなのか?


選択式の足切りで不合格になった人は、こんな気持ちにもなってしまいます。
選択式が運ゲーと言われる要素は、
- 試験の出題範囲がとても広いし、
- 細かい部分から難問や奇問が出題されるし、
- 白書から見たことがない問題も出題される。

あと1点に泣く人が本当に多いじゃ(>_<)
とは言え、選択式についての王道の勉強方法と正しい問題の解き方があるのも事実です。
序盤は基本のインプットを中心に、後半は模試などのアウトプットにも力を入れる。学習のタイミングについては、質問②も参考にしてくださいね。

質問②対策を始める最適な時期はいつから?
本格的に選択式対策を始める時期は、GW以降で十分でしょう。
それまでの期間は、
- 科目1周目として基本をインプットする
- テキストと過去問を反復学習する
という基礎固めに全力を注ぎましょう。

基礎知識がないと対策の効果も発揮しないんじゃ(^^)
逆に基礎・基本を固めることで、8割は対策できたことにもなり得ます。
再受験生は科目1周目から、
- テキストの太字・赤字を意識する
- 過去問の論点をより意識する
という学習を取り入れても良いでしょう。
とは言え、再受験生の人もGWまでは基礎・基本の定着と復習を中心に学習するべきです。筆者は、選択式に力を入れ過ぎて択一式で不合格になった人も見てきました。

質問③スクールの活用が効率的な理由は?
スクールを活用することは、選択式対策に大きく貢献してくれます。
- 論点やポイントがまとまったテキスト
- 質の高い予想問題とわかりやすい解説集

限りある時間でこれらは大きな助けとなる(^^)
特に膨大な白書の対策も効率的に学習できますよ。
スクールが教える問題の解き方はこの記事と重複することも多いとは思います。但しリアルな講義を受講したり、テキストを手に入れる価値は高いですよ。
筆者も受験生の時は、知人が受けた模試の「選択式問題」はチェックしていたぐらいです。

スクールについては、アガルート社労士アカデミーを検討してみましょう。
- 受講生の約3人に1人が合格している
- 情報量は多いけどきっちりとしたカリキュラム
- 5月以降には選択式集中特訓講座もある
短期集中的に選択式の解答力を向上できる可能性がありますよ。
まとめ:社労士試験の選択式は運ゲーではない

社労士合格の大きな障壁になるのが選択式試験です。
断言しますが、社労士試験に「運」で合格した人は絶対にいません。そして、運ゲーではなく、王道の勉強方法と問題の解き方は存在します。
王道の勉強方法とは、
- 択一式の過去問をしっかり解く
- テキストの赤字や太字を抑える
- GW以降に模試や予想問題を解く

何度も言うが、まずは基礎知識を整えることが大切じゃ(^^)
王道の正しい問題の解き方とは、
- まずはテーマと論点を理解する
- 選択肢を見ずに解答を書き出す
- 選択肢をグルーピングする
- 前後の言い回しから判断する
- ダブルマークも最終手段

勉強は長い道のりで辛い時もありますが、運ではなく必ず報われる瞬間はやってきます。
それではまたっ。