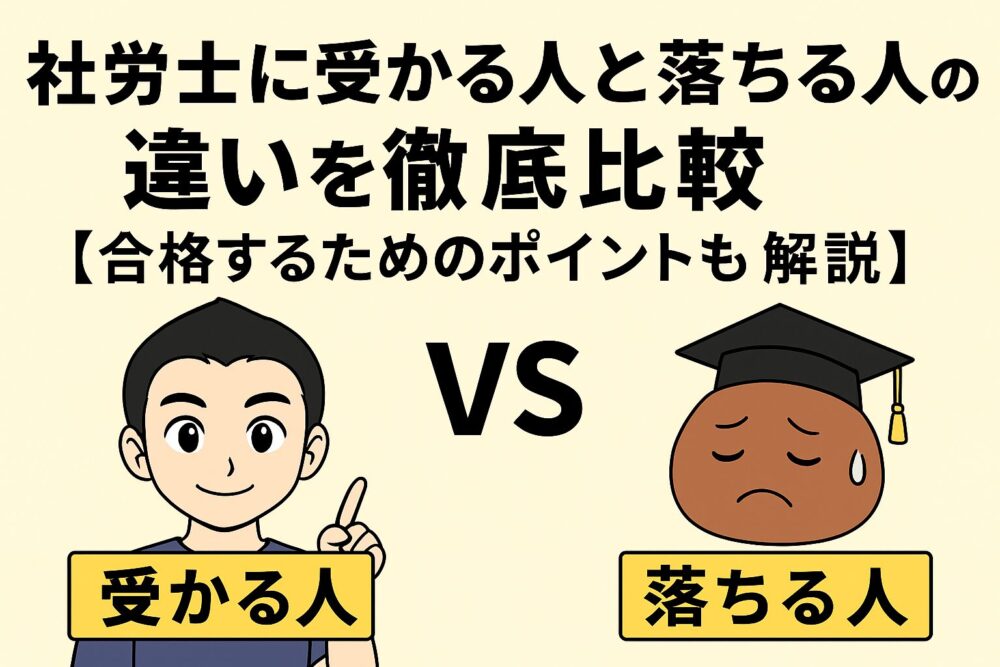こんにちは、社労士のタクヤです。


こんな人のための記事です。
筆者は社労士試験に、受験生として2年間、講師として5年間と長く携わってきました。
経験から断言できるのは、社労士試験に「受かる人」と「落ちる人」には、紙一重であっても明確な「差」が存在する事実です。

この記事では、その決定的な違いと合格への最短ルートを解説するぞ!

社労士に受かる人と落ちる人の3つの違い
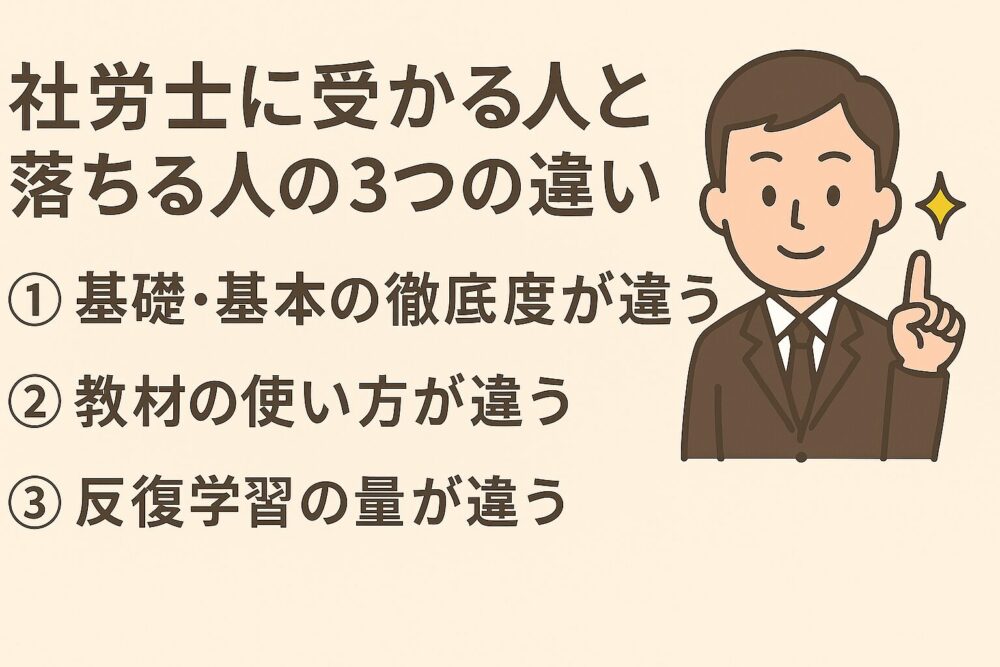
違い①基礎・基本の徹底度が違う
社労士試験では、基本を落とす=不合格を意味します。
受かる人と落ちる人の違い➊
受かる人:正解率の高い基本問題は絶対に落とさない
落ちる人:応用問題に目が行き、基本問題を落とす
断言できるのは、基礎・基本を固めておかないと「合格できない」という現実です。

結局は「地味な勉強」が合否を分けるんじゃ!
基本を徹底する人は、次の3つを守っています👇
- テキストと過去問を繰り返す
- 全体像をつかんでから理解を重ねる
- 重要語句を「自分の言葉」で説明できる
「基本の繰り返し」こそ、合格者が毎日やっていることなんですよね。

違い②教材の使い方が違う
受験勉強において、たくさんの教材や予想問題に手を付けるのは避けましょう。

理由は、「中途半端」こそ、命取りになるからじゃ!
受かる人と落ちる人の違い➋
受かる人:与えられた教材を「丁寧」に学習する
落ちる人:色んな教材に手を付けて「中途半端」になる
学習初期〜直前期の理想的な構成は下記の通りです👇
| フェーズ | 使用教材 | ポイント |
| 初期(〜4月) | テキスト+過去問 | インプット中心で全体像を理解 |
| 中期(5〜7月) | テキスト+過去問+模試 | 問題演習+弱点把握 |
| 直前期(8月) | テキスト+過去問+模試+法改正 | アウトプットと基本の復習 |
逆に色んな教材を使用するデメリットは、
- クセのある予想問題が混じっている
- 復習の時間を取らないと定着しない
- 解けないと必要以上に自信をなくしてしまう
など、悪影響も多いです。
予想問題に手を出すのは、基本教材をばっちり仕上げてからにしましょう。

違い③反復学習の量が違う
暗記が苦手でも、反復学習すれば誰でも覚えられるのが社労士試験です。

合格した人が口にする勉強方法は3つじゃ!
❶テキストを7回は繰り返し読んだ
❷過去問を10回は繰り返し解いた
❸模試の復習を2回は繰り返した
とにかく繰り返し、反復学習しているんですよね。
逆に一般の受験生がよく口にするのは、
- 昔から暗記が苦手だったから、、、
- 歳だし若い人みたいに覚えられないし、、、
- お酒を飲んだらつい忘れてしまって、、、
大体こんな感じです(笑)

筆者の場合は過去問を全科目30回は繰り返し学習しました。そして、「〇」と「×」とその理由は全て完璧にすることで、成績も上がりました。
受かる人と落ちる人の違い➌
受かる人:とにかく繰り返し、反復学習をしている
落ちる人:覚えるためにノートなど別の資料を作る

社労士に受かる人と落ちる人はどこで運命が左右される?
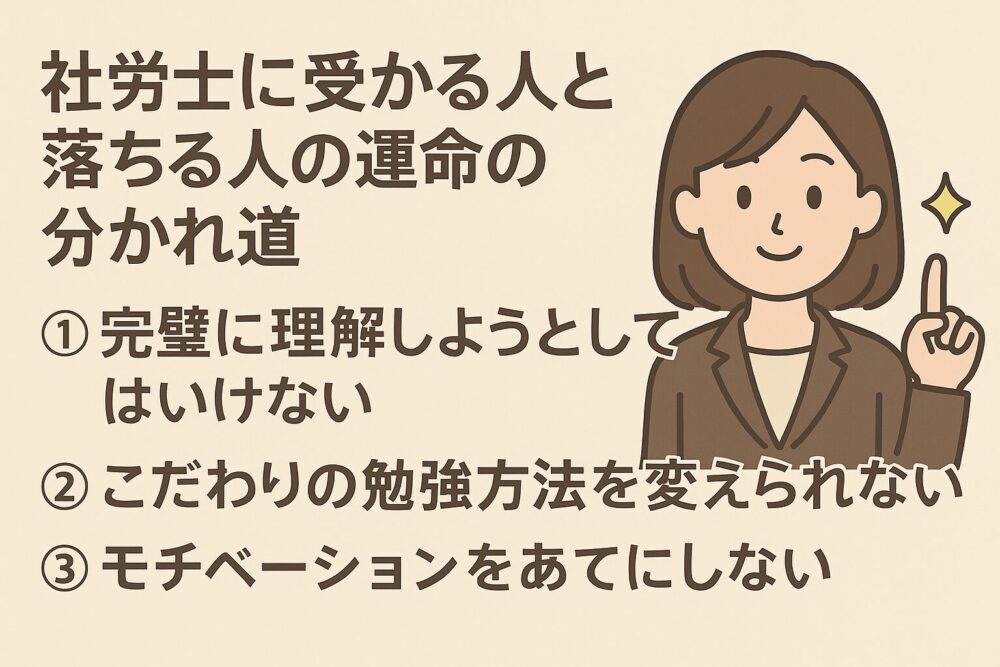
運命①完璧に理解しようとしてはいけない

「理解できるまで進めない」タイプは要注意じゃ!
なぜなら、まず大切なのは科目の全体像を理解することだからです。
ポイント
〇まずは70点を目指す勉強法
×1ページずつ順番に理解する(完璧主義)
全体を理解してこそ、「わかる」・「理解できる」内容もあります。
効率的に合格レベルに到達するためには、
- 学習する科目の全体像の把握をする
- 基礎を抑えてまず”7割”の理解度に到達する
この2つを意識して勉強に取り組みましょう。

受かる人と落ちる人の違い➍
受かる人:全体像を掴んでから、難しい単元に戻る
落ちる人:理解できない箇所で立ち止まる

運命②こだわりの勉強方法を変えられない

常に自分オリジナルな勉強方法の人は危険じゃ!
なぜなら、素直に取り入れる姿勢がないと、伸び悩んで頭打ちをするからです。
ぶっちゃけ社労士試験の勉強には、
- 深く理解が必要なところもあれば、
- 丸暗記で大丈夫なところもある。

でも伸び悩んでいる時こそ、
✅講師や合格者の勉強方法をまねてみる
✅聞く耳をもって王道の勉強方法を取り入れる
これこそが合格の近道になることは、肝に銘じておきましょう。
受かる人と落ちる人の違い➎
受かる人:結果に応じて柔軟に方法を変える
落ちる人:点が取れなくても勉強方法を変えない
運命③モチベーションをあてにしない
合否をわける一番大きい分かれ道は、「モチベーション」に左右されることです。
長丁場の受験勉強に必要なのは、次のマインドです。
×モチベーションを上げること
ではなく、
〇「とにかくやる」と決めて継続すること
結論として、モチベーションに頼るのは危険です。

人間の上がった気持ちは、いずれ必ず下がるものじゃ!

そんな日も絶対にありますが、

最終的には「習慣化すること」が一番の理想です。その習慣化までの、「モチベーションが上がらない日」をいかに踏ん張れるかが運命の分かれ道です。
落ちる運命の人③
受かる人:モチベーションという概念がない
落ちる人:モチベーションに左右されて勉強時間が変わる

社労士に受かるためにすべきこと3選
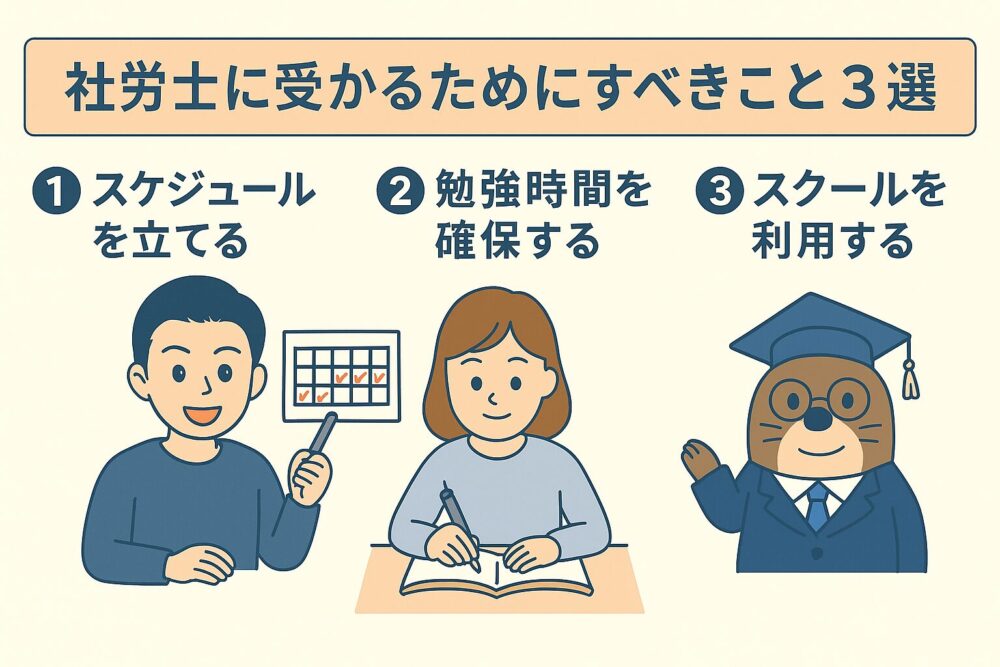
すべきこと①スケジュールを立てる
長丁場の受験勉強だからこそ、3つのフェーズに分けた学習計画を立てましょう。
フェーズ❶:学習初期(~4月)
フェーズ❷:学習中期(5月~7月)
フェーズ❸:直前学習期(8月)

各フェーズの学習ポイントは下記を確認じゃ!
フェーズ❶:学習初期(~4月)
- 各科目の1周目を終わらせる
- テキストと過去問を中心に学習
- インプットを中心とした学習
フェーズ❷:学習中期(5月~7月)
- 科目の2周目として知識を定着させる
- ここからアウトプットにも力を入れる
- 模試にも1回~2回は挑戦する
フェーズ❸:直前学習期(8月)
- 複数の科目を同時並行で試験対策
- 油断して基礎・基本は落とさない
- どれぐらい反復学習できるかが鍵

すべきこと②勉強する時間を確保する
スケジュールを立てたら、実践するための具体的な方法を考える必要があります。

時間を活かすために、まずは下記を整理して書き出してみましょう。
【ポイント】
✅自分の1日の使い方を点検する
✅まとまった時間の活用を考える
✅スキマ時間の活用を考える
✅更に作り出せる時間を考える
✅1日のやることを絞る
時間確保に関する人気記事
»社労士試験の勉強時間をつくる15の具体的な方法【仕事・家庭との両立術】
ちなみに筆者が受験生の時は、
- 通勤時間の往復で1時間30分
- 平日は退社後にカフェで2時間
- 土日は平均6時間~8時間
ぐらいは勉強していました。

合格者は「1,000~1,500時間」は勉強したと答える人が多い印象じゃ!

すべきこと③スクールを利用する
予備校などのスクールを活用した方が断然よいです。
なぜなら社労士試験は、
- 10科目と範囲が広いし、
- 法改正など新しい情報も必要だし、
- 問題の解き方にはコツがあるから。

難しく感じて、嫌になっては本末転倒じゃ!
但し、合格率が10%以下の試験なので、
- 専門用語はそれなりに多いし、
- 解釈しにくい法律もあるし、
- 丸暗記では理解できないところもある。
そんな中で、やはりスクールは独自のノウハウをたくさんもっているし、学習のペースメーカーとしても最適です。
スクールがもっているノウハウ
❶勉強方法についてのノウハウ
❷正しく理解するためのノウハウ
❸試験で得点を積み上げるためのノウハウ
おすすめ社労士スクール
»アガルートアカデミー社会保険労務士試験講座

社労士に受かる人の特徴を理解して合格しよう

社労士に「受かる人」と「落ちる人」には明確な違いがあります。
社労士に受かる人の勉強方法の柱は3つです。
❶まずは基礎・基本を完璧にする
❷教材はテキストと過去問を中心に使用する
❸とにかく繰り返し、反復学習する
そして大切な姿勢は、
- 不必要な完璧主義や自分のこだわりをもち過ぎず、
- モチベーションに左右されずに「とにかくやる」。

忙しい社会人が挑戦するなら計画立ても忘れずに!
社労士に挑戦するならば、
- 勉強のスケジュールを立てて
- どうやって時間の確保をするか
まで具体的な計画を立てましょう。
断言できるのは、社労士試験に合格する人は、繰り返し・反復学習をがんばった人というシンプルな事実です。
×「頭がいい」「記憶力がある」
ではなく、
〇「見たことがある」「やったことがある」

それではまたっ^^